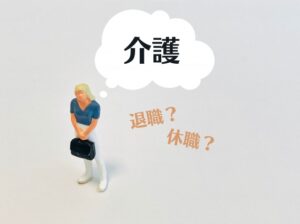働く介護者の孤独
仕事と介護の両立支援
という言葉がありますが
”両立”という言葉の意味を考えると
両方とも自分でやらなければいけない
と考えてしまう人もいるかもしれません。
介護は自分で頑張ろうとせずに
できる限り介護の専門家に任せるもの
両立支援ではなく
介護の専門家とつながるための支援
が本来必要なことと考えています。
先日
以下のようなニュース記事が掲載されていました。
50代女性が、子育てをしながら脳腫瘍の夫を介護していた約10年前の苦悩を振り返った。
女性は当時、子どもを持つ女性管理職として、ロールモデルとなることを期待されていた。一つ課題をこなすと、すぐに新たな課題を与えられる。家での介護と育児で疲弊していたが、断ることも、助けを求めることもできず、手を抜けなかった。通勤途中、涙が止めどなく流れるようになり、「参っている」と自覚した。そして職場を離れた。2017年から認知症の父親とパーキンソン病の母親、昨年から別居の叔父も介護している会社員の女性(49)も、介護と仕事の両立の難しさを吐露した。
一人っ子で頼れる身内はいない。介護に時間をとられることを想定し、作業マニュアルを整え、早めに引き継ぎを行い、担当業務に影響が出ないように心掛けてきた。しかし、どんなに頑張っても、「休みが多い」「負荷はかけられない」と思われているように感じた。疲労が募り、打ち合わせを失念することもあった。昇進はあきらめた。
「両立より、介護に『全振り』した方が楽かもしれない」。心が折れそうになることもある。「介護と仕事にかける比重は人それぞれ。『どうしたい?』と聞いてもらった上で、会社と個人の最適解を探れるようになれば」と訴えた。
⇒通勤中に涙「休ませてと言えなかった」、仕事と介護の両立に疲弊(読売新聞)
仕事をしながら介護も行う方の
リアルな姿が書かれています。
あらためて
職場の中で
介護のことを悩まずに話せる環境
相談できる環境を
整備することの大切さを感じます。
また
「両立より、介護に『全振り』」という表現を見て
本来であれば
介護の専門家に『全振り』すべき
ということを伝えたくなります。
もちろん
介護の専門家に『全振り』するには
経済的な負担もあるため
簡単にできることではありませんが
そういった選択肢を考えられることも
めちゃくちゃ重要だと思っています。
企業としては
介護休業制度のもと
社内の就業規則等を整備するだけでなく
介護が必要な家族がいる従業員に対して
従業員が声をあげるのを待つのではなく
企業側から支援していくような体制
介護の専門家とつながれる支援など
検討いただけると良いかと思います。
投稿者プロフィール

- 2005年、介護ベンチャー企業に入社。グループホームの開業準備、行政への指定申請、入居相談、運営管理業務に携わる。2010年には、介護複合施設の開業準備から運営管理までを経験。その後、有料老人ホーム、デイサービスの管理者として現場経験を重ね、2012年からはデイサービスのフランチャイズ本部にて、フランチャイズ加盟店に対しての開業研修、運営支援業務に携わる。
最新の投稿
 介護情報2026年2月15日大学キャンパスを地域住民に開放
介護情報2026年2月15日大学キャンパスを地域住民に開放 介護情報2026年2月14日高齢者でもお花見に行きやすい場所
介護情報2026年2月14日高齢者でもお花見に行きやすい場所 介護離職対策2026年2月13日研修や相談窓口は専門家に依頼してみる
介護離職対策2026年2月13日研修や相談窓口は専門家に依頼してみる 介護離職対策2026年2月12日リニューアルした介護休業制度特設サイト
介護離職対策2026年2月12日リニューアルした介護休業制度特設サイト